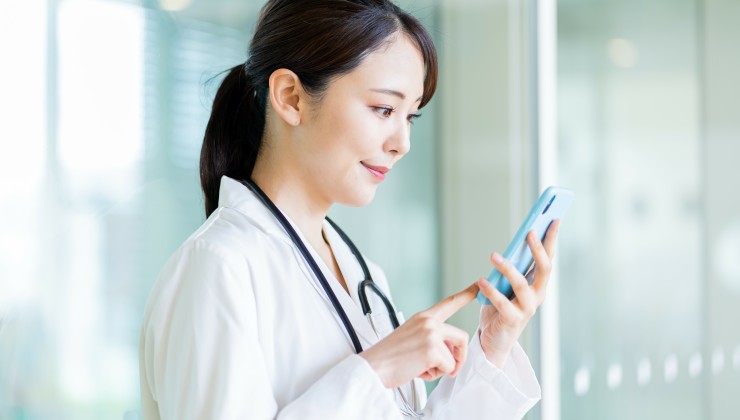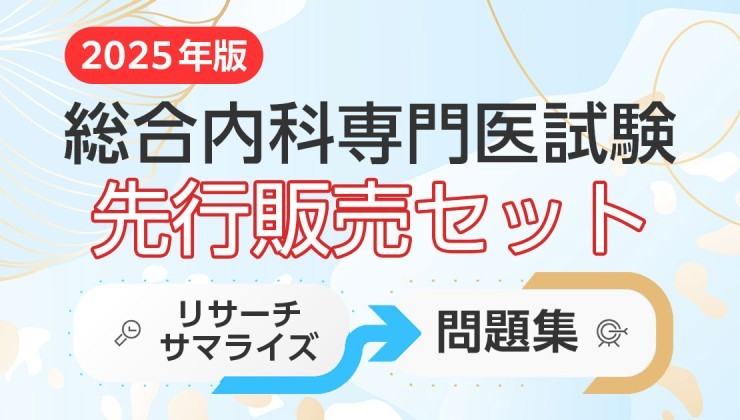専門医になるためには時間と労力がかかります 医学部を卒業してから長い研修を経ているので、モチベーションを維持しながら専門医を目指すには、専門医になるメリットを知っておく必要があるでしょう。 今回は専門医の概要を解説していきますので、志している方はぜひチェックしてみてください。
専門医とは?概要を解説
専門医はスーパードクターであるという認識を持たれがちですが、日本専門医機構は専門医のことを「神の手を持つ医師やスーパードクター」ではないと明言しています。*1 では、「専門医」とはどのような医師なのか、また他の医師とはどういった点に違いがあるのか見ていきます。
*1:「専門医制度の現状と課題 今後の医師養成の在り方と地域医療に関する検討会資料」(厚生労働省・医政局)https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000163149.pdf
「専門医とは」
一般社団法人日本専門医機構は、専門医を次のように定義しています。
<専門医の定義>
「日本専門医機構が認定する「専門医」とは、それぞれの診療領域における適切な教育を受けて、十分な知識・経験を持ち患者から信頼される標準的な医療を提供できるとともに、先端的な医療を理解し情報を提供できる医師」
この定義からもわかるとおり、専門医は標準的医療を提供でき、患者から信頼される医師のことを指します。
「認定医」「指導医」「専攻医」との違いとつながり
専門医と似た用語に、認定医、指導医、専攻医があります。 それぞれ異なる医師を指しますが、つながりがあるので確認していきましょう。
専攻医は専門医の前の段階
専攻医は、臨床研修を修了した医師で専門研修に参加している医師の名称です。 専門医の前の段階の医師のことを専攻医と呼びます。
認定医は学会が認定した医師
認定医は、それぞれの学会が基準を設け、それをパスした医師に与えられる資格です 関連する臨床の知識と経験が基準に達しているか、専門とする分野の業務に一定期間携わり該当する治療を一定以上行うなどの実績が求められます。 認定医制度を設けていない学会もあります。
指導医は認定医・専門医を指導する立場の医師
指導医には、知識と経験を経て学会の基準をクリアするだけではなく、認定医や専門医を育成、指導するための能力が求められます。
認定医・専攻医→専門医→指導医
認定医、専攻医、専門医、指導医はステップアップ、キャリアアップの面でつながっています。 ①医師としての経験を積んで認定医または専攻医になる ②専門研修と専門医試験を経て専門医になる ③指導法などを習得して指導医になる という流れとなります。
専門医になるメリット
日本専門医機構は「専門医はすべての医師が取得しなければならないものではなく、その取得は医師としての自律的な取り組みである」としています*2
*2 「新たな専門医制度の背景と現状(改)」(厚生労働省) (https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000508257.pdf)
ただし、日本専門医機構が認定した専門医になると多くのメリットを得ることができます。
スキルアップ、ステップアップができる
専門医になるための専門研修を受けると、確実なスキルアップをすることができます。 専門研修は、専門研修基幹施設の認定を受けた病院の専門性、診療実績、指導体制が整っている環境で専門研修指導医から指導を受けることができます。 専門研修指導医はその領域で十分な経験を積んだ教育と指導の能力を持つ医師なので、スキルアップにつながる技術や知識を豊富に身に付けることができます。 また、認定医から専門医へとステップアップした場合には、給料や報酬が上がることもあります。
信頼を得ることができる
かつての専門医制度での専門医は、学会によって専門医に課す基準が異なっていたため、提供する技術や知識に差がありました 一方、新専門医制度下の専門医は、試験や基準が統一されたことにより専門医の質向上が期待できます。 今後この新専門医制度がより浸透していけば、先端的な医療を理解しながら標準的な治療を提供できる専門医が増えていくので、ますます専門医への信頼度が高まり、社会的な信用を得ることができるでしょう。 また、他の医師からも専門性の高い知識を持った専門医は信頼を得ることができます。
専門医になるには
では実際に専門医になるにはどうすればよいのでしょうか。 ここからは実際に専門医になるために必要な期間や研修内容を紹介します。
専門医になるには最短で30歳
専門医になるには、最短で30歳ほどです。 18歳で大学医学部に入学した場合、卒業して医師免許を取得するのは6年後の24歳です。 そこから2年の臨床研修を受け、次に専攻医となって専門研修を3年以上受けてから専門医資格を取得するため、どれだけ早くても29歳以上です。*3 診療科によっては、専門研修を「基本領域の専門研修3年」と「サブスペシャルティ専門研修1~3年」と年数に違いがあります。
*3 「新たな専門医制度の背景と現状(改)」(厚生労働省) (https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000508257.pdf)
長い研修期間の内容もかなりハードです。 例えば、内科専門医制度の専門研修の内容は以下のとおりです。
主担当医として、カリキュラムに定める全70疾患群を経験し、計200症例(外来症例は20症例まで含むことができる)以上を経験することを目標とする。 修了認定には、主担当医として通算で最低56疾患群以上の経験と計160症例以上(外来症例は1割まで含むことができる)を経験し、登録しなければならない。 指導医は専攻医として適切な経験と知識の修得ができていると確認できた場合に承認をする。 不十分と考えた場合にはフィードバックと再指導を行う。
日本専門医制度概報 より引用
このように専門医資格を取得するには、専門研修を修了して、専門医試験を受けて合格しなければならないので実力と経験を積む長い道のりといえます。
新専門医制度により資格が必要に
旧制度では、各診療科の学会が定めた基準を満たせば専門医になることができ、学会によっては試験もありませんでした。 しかし2018年から新専門医制度が導入され、専門研修を修了して専門医試験に合格しないと専門医の資格を得ることができなくなりました。 例えば内科専門医制度の専門医試験の内容は以下のとおりです。
試験は筆記試験(全250題)
●対象領域:総合内科、消化器、循環器、内分泌、代謝、腎臓、呼吸器、血液、神経、アレルギー、膠原病および類縁疾患、感染症、救急 ●出題構成:上記領域から一般問題、臨床問題がそれぞれ構成される ●出題および解答方式:マークシートによる回答形式はAタイプ(単純択一形式)、X2タイプ(多真偽形式、定数2)を想定
日本専門医制度概報 より引用
専門医になるには試験対策が欠かせません。
専門医試験対策はドクスタがおすすめ
専門医試験対策を効率的に進める方法として「ドクターズスタディ」通称ドクスタの利用がおすすめです。
専門分野に特化した学習
「ドクターズスタディ」は、基本領域の内科専門医試験と外科専門医試験、そしてサブスペシャリティ領域の総合内科専門医試験に特化しています。 学習方法は、テキストと講義(動画)の2種類です。
例えば総合内科専門医試験の対策教材「総合内科専門医試験リサーチサマライズ」では、第51回総合内科専門医試験受験者へのヒアリング内容を分析し、難関試験の傾向と対策をレクチャーしているので、Dr. 孝志郎の臨床アドバイスによって勉強の方向性を定めることができ、効率的な学習が可能です。
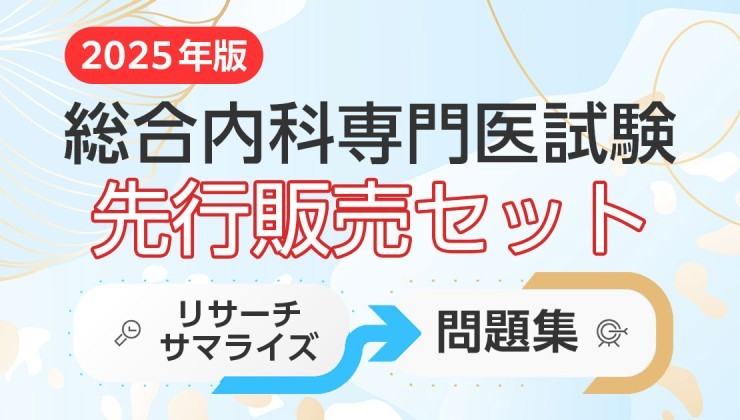
講師は医師関連試験のカリスマ、Dr.孝志郎
動画の講師を担当するのは、医師関連の試験対策のカリスマ講師であるDr.孝志郎です。 Dr.孝志郎は宮崎大学医学部卒の総合内科専門医で、2007年から「ドクターズスタディ」の講師を務めています。
受講した若い医師たちから「類稀なる予想的中力」「講義はわかりやすくて聞き取りやすい」、そして「明るく楽しい人柄」と評されています。 医師国家試験の直前に行われる講義では、医学部生が6,000人集まったこともあるので、ぜひDr.孝志郎の講義を体感してみてください。
まとめ
専門医は、神の手を持つスーパードクターではなく、先端的な医療を理解し、標準的な医療を提供できる医師のことを指します。 専門医になるための道のりはハードですが、専門医になるとスキルアップ・ステップアップが期待でき、社会的な信用、他の医師からの信頼を得ることができます。 新専門医制度下で専門医になるには、試験対策が必要になりました。 専門医になるための知識を効率よく身に付けるには、新専門医制度に対応した「MEC Doctor’s Study」通称ドクスタがおすすめです。 ドクスタのテキストと講義動画を活用し、自分のペースに合わせた学習を進めてみてはいかがでしょうか。