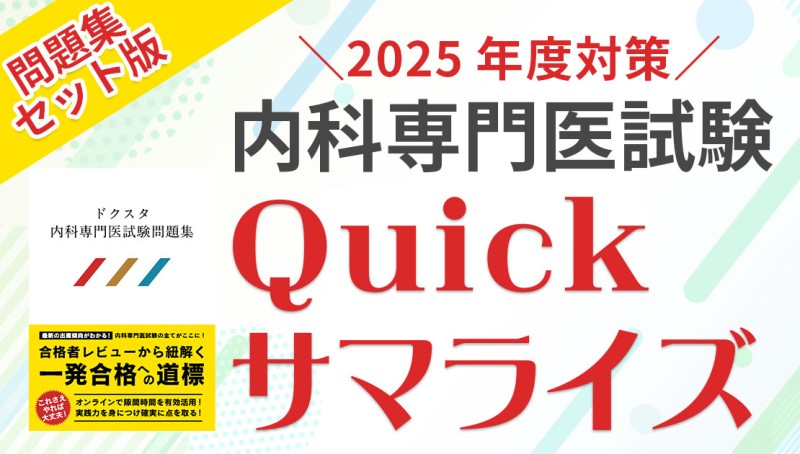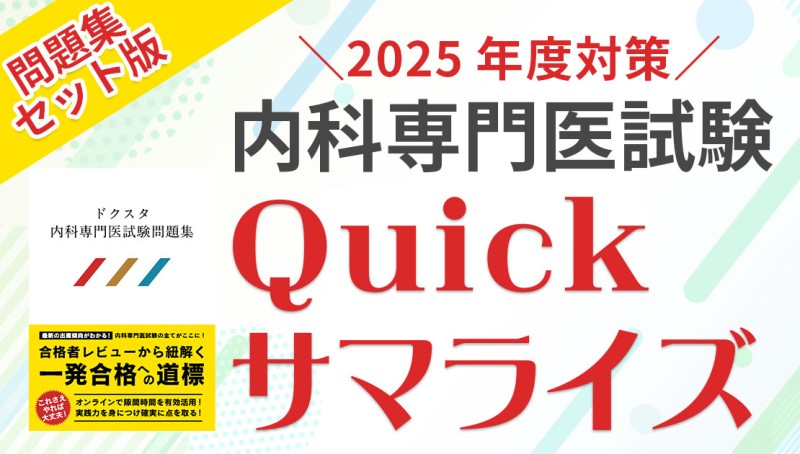2018年に新専門医制度が誕生し、新制度下での内科専門医試験は3年の研修プログラムを経て2021年度に第1回が開催されました。
新専門医制度の試験データは少ない上に、従来のものとは形式や内容も変化しており、難易度が把握しづらいのが現状です。
では、これまでの内科専門医試験の合格率や難易度はどのくらいだったのでしょうか。
内科専門医試験の難易度は?
新専門医制度の内科専門医試験は実臨床を反映した臨床問題を想定して作成されており、従来のようにテキストベースの対策だけでは対応しきれない可能性もあります。
これらを踏まえて、2024年度の合格率と2025年度試験への対策方法について解説します。
試験問題は合格率約9割を想定して作成
新専門医制度の内科専門医試験は、合格率約90%を想定して試験問題が作成されています。
一方、従来の前段階にあたる認定内科医試験の実際の合格率は直近10年で約80〜90%、旧制度における総合内科専門医試験は約60〜80%と振れ幅があります。
これらを考慮すると、新専門医制度の難易度は低いように感じるかもしれませんが、総合内科専門医試験とは異なり、3年以上の研修プログラムを経て、病歴要約29篇を提出、一定以上の評価を受ける必要があるため、合格率のみで一概に難易度を判断することはできません。
とはいえ、研修プログラムを修了した医師であれば本来100%合格してもおかしくはないでしょう。
また、試験は領域別の出題よりも、診断から治療までを全人的に判断できるかを問う問題を多く取り入れる方針であることが明かされています。
2024年度の合格率は93.6%
2024年度(第四回)内科専門医の筆記試験における合格率は93.6%でした(日本内科学会HPより)。
| 年度 |
受験者数 |
合格者数 |
合格率 |
| 2021 |
1,965 |
1,856 |
94.5% |
| 2022 |
2,495 |
2,246 |
90.0% |
| 2023 |
2,833 |
2,416 |
85.2% |
| 2024 |
2,997 |
2,804 |
93.6% |
近年の傾向について
表の通り、第三回のみ合格率が大きく下がっています。今後どう推移していくかについては不透明であるものの、基本的には合格率90%台で推移していくとドクターズスタディでは予想しています。
いずれにせよ、合格率の変動に左右されない効率的・確実な試験対策が重要になるといえるでしょう。
2025年度の試験日程について
内科専門医・総合内科専門医について、本年の試験日程が学会より発表されました。
いずれも、2025年1月時点での情報ですので、最新情報については学会HPをご確認ください。
◆2025年度 第五回 内科専門医 資格認定試験
試験日:2025年5月25日(日)試験時間 9:00 ~ 16:40(予定)
出願期間:2025年1月23日(木)~2025年4月15日(火)23:59まで(期限厳守)
新たに内科専門医試験が導入され、専門医のハードルが下がった可能性も
新専門医制度によって合格率や難易度だけではなく、内科専門医の取得方法も変わりました。その中でも着目すべきは専門医を取得するために受ける必要があった認定内科医試験が廃止されたことです。
ここからは取得方法が具体的にどのように変わったのか、それに伴って起こりうる変化について解説します。
受験資格の取得方法が変わった
従来の制度と新専門医制度の取得に関する違いは、主に取得するまでの過程や研修年数です。
2017年以前、内科専門医の受験資格は認定内科医試験に合格し、その後2年以上の研修を終えて初めて得ることができました。
加えて、認定内科医試験を受験するためには後期研修に該当する3年以上の研修期間が必要で、試験の合格率は約8〜9割と、落ちる医師もいました。
一方、新専門医制度に移行すると、2016年以降に医師免許を取得した場合、後期研修にあたる3年以上のプログラム研修と病歴要約29篇の提出をもって受験資格が認められるようになりました。
このように受験資格を取得するまでの過程や研修年数は大きく変化しています。
認定内科医試験の廃止に伴う変化
先述のとおり、従来の制度における専門医取得の必須条件となる認定内科医試験は廃止されました。
新専門医制度では専門医試験を受験するための最低研修期間がこれまでの3+2年の5年から3年に短くなったため、内科専門医取得のハードルが下がったという見方もできます。
認定内科医を取得した方、特に新専門医制度への移行期に取得した医師の中には、認定内科医の取得が無駄だったと思う場合もあるかもしれません。
しかし、認定内科医を取得していると3年以上のプログラム研修や病歴要約29篇の提出が免除されるため、これらを有効活用することで新専門医制度下でもスムーズに専門医取得が可能となっています。
総合内科専門医試験は残っている
認定内科医試験は廃止され、研修プログラムおよび内科専門医試験に置き換わりましたが、総合内科専門医試験は新専門医制度に移行した後も残っており、今後も取得することが可能です。
従来の制度では認定内科医を取得することで総合内科専門医試験の受験資格が得られるようになっていました。
新専門医制度での内科専門医試験に関する運用はこれからとなりますが、この新制度における内科専門医となることで総合内科専門医試験を受験することができます。
内科専門医を取得後、総合内科専門医取得まで進むことでより専門的な知識や経験を得ることができると同時に、それを資格として証明できるようにもなります。
合格を目指そう!ドクスタの内科専門医試験対策
ここまで解説してきたように、内科専門医試験は過去の試験データの集積は乏しく、発行日の古いテキストではカバーしきれない領域が出てきます。
学習テキストは新しいものを揃え、忙しい日常診療のなかで効率的・効果的な試験対策を行なっていくことが重要です。
Dr. 孝志郎によって分析・開発された対策講座で効率的に学習
過去の内科専門医試験を分析すると、試験で求められる知識は医師国家試験とかなり重複しています。
さらに、直近の医師国家試験の問題を解いておくことが非常に重要であり、内容的にもトピック性があることが分かっています。
こうした背景から、ドクターズスタディでは「★2025年度最新★内科専門試験対策セット<問題集+Quickサマライズ>」を公開しています。
本セットでは、全884問を収録した「内科専門医 試験問題集」で全体像を把握し、厳選50テーマを解説する「Quickサマライズ」の講義動画で理解を深め、知識を広げることができます。
過去問を自分で集めたり分析したりする手間を省き、「内科専門医試験で問われるであろう部分」に集中して学習することが可能です。