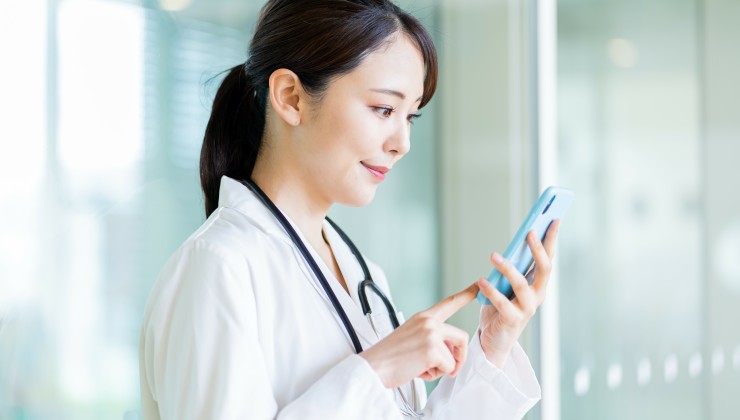専門医試験は2017年まで各領域の学会(小児科であれば日本小児科学会)が独自にプログラムを決定していましたが、領域によって難易度に差があることが問題とされていました。そのため、2018年より学会と独立した中立的な機関である日本専門医機構が中心となって専門医試験を運用しています。
今回は、新制度下の小児科専門医試験の概要や合格率について解説します。
>>新専門医制度について詳しく知りたい方はこちら
小児科における専門医試験の概要と合格率
小児科の専門医試験を受験するためには3年間の研修が必須です。したがって、2018年より新制度が導入されたものの、新制度下での小児科専門医試験が始まったのは2021年度からです。
ここでは小児科専門医試験の概要と合格率を具体的に紹介します。
参考: 告示|日本小児科学会
専門医試験の概要
小児科の場合、2017年度と2018年度は実質、移行期間となっています。研修を2016年度以前に開始したか、2017年度以降に開始したかによって受験資格や提出書類は異なります。2016年度以前に開始した場合は旧制度の条件で小児科専門医試験を受験しますが、2017年度以降に研修を始めた場合は以下の条件が適用されます。
受験資格
受験資格は次の2つを満たす必要があります。
・ 小児科学会の会員歴が連続3年以上、もしくは通年5年以上であること
・ 2004年以降の医師国家試験合格者で、2年間の初期臨床研修を修了後,日本小児
科学会および機構が認定した小児科専門研修プログラムにより3年以上の研修を修了または研修修了見込みであること
提出書類
提出書類は以下の通りです。
・受験出願書
・研修終了(見込)証明書
・症例要約指導証明書
・症例要約・指定疾患チェックリスト
・症例要約
・CD-R(症例要約を保存)
・学会が指定する医学誌への論文掲載証明書類
・論文チェックリスト
・小児科(専門医/専攻医)臨床研修手帳
・臨床研修修了登録証のコピー
提出書類のうち旧制度と異なる特徴があるのは、研修終了(見込)証明書に記載された「臨床現場における評価」が試験の書類提出時に審査対象となることです。
また、原著論文(症例報告も含む)を1つ以上執筆しなければなりません。査読中のものは受理されないため、早いうちから取りかかっておくことをおすすめします。
小児科の専門医試験に合格した後は5年毎に更新手続きが必要となります。
試験科目は3つ
試験科目は旧制度と大きく変わりはなく、以下の3つです。
(1)症例要約
症例要約を30症例(3症例までは外来症例でも可)記載します。小児科に関する分野をできるだけ偏りなく提示することが求められます。
(2)筆記試験
医師国家試験のMCQ形式に準じた140題が出題されます。そのうち一般問題(A問題)は95題、症例問題(B問題)は45題です。小児科専門医の必須知識を中心に、地域総合小児医療に関する問題の解決能力を図る課題が提示されます。
(3)面接試問
提出した30症例の中の2症例について、2人の面接委員により試問が行われます。どの2症例が当たるかは事前に知らされません。ここでは小児科専門医としての適切なコミュニケーション能力や問題解決能力、態度を評価されます。
合格率は70%以上
次に小児科専門医試験の合格率について解説します。
2022年現在、新制度での小児科専門医試験は2021年度の1回のみしか開催されていません。データが少ないことが難点です。しかし、後で述べるように問題形式や難易度は旧制度と大きく変わりはないため、合格率が大幅に変動する可能性は低いでしょう。
2012年〜2016年における合格率の平均は次のようになります。
| 症例要約 |
筆記試験 |
面接試験 |
| 約98% |
約76% |
約100% |
これらのデータより合格を左右する大きな要素は筆記試験であることがわかります。なお、同期間で小児科専門医の認定がされたのは約74%の受験者です。順当に考えれば新制度下の小児科専門医試験も合格率70%以上となることが予想できます。
参考:動き出した新専門医制度|日本小児科学会
小児科における専門医試験の傾向と対策
これまで小児科専門医試験の概要と合格率について紹介してきましたが、ここからは傾向と対策を解説します。
専門医試験の傾向
先述の通り、新制度における小児科専門医試験は旧制度と比較して大きく変更された部分はほとんどありません。プログラムの研修内容や専門医試験の難易度、様式も旧制度の内容が引き継がれています。
特出すべき変更点を挙げるのであれば、新専門医制度のプログラム制の理念を踏まえ、研修課程における評価の強化を行ったことです。具体的に以下の内容が導入されました。
| 簡易版臨床能力評価法(Mini -CEX) |
専門医と患者が関わる様子を観察して評価する方法 |
| 360度評価 |
指導医だけでなく、専門医を取り囲む全ての人たちが専攻医を観察し他業種を含め様々な視点からの評価をする方法 |
| マイルストーン |
研修の節目ごとに設定した研修目標に基づき評価する方法 |
| DOPS |
専攻医が実際に診療手技を行うときに指導医がチェックリストを基に評価する方法 |
なお、手技観察評価(DOPS)に関しては記載義務はありません。手法観察評価とは専攻医が実際に診療手技を行うときに指導医がチェックリストを基に評価する方法です。
専門医試験の対策方法
ここでは専門医試験の対策方法について説明します。症例要約は試験を申し込む時に余裕を持って準備し、試験日まで筆記試験の対策を行っておくことが小児科専門医試験合格の秘訣です。
学会のホームページから過去問をダウンロード
小児科の専門医試験は旧制度のものも含めて過去問をしっかりと解くことが試験対策につながります。過去問は全ての回ではありませんが、日本小児科学会のホームページで公開されています。ダウンロードして対策を行いましょう。過去問へのアクセスは会員専用ページへのログインが必要です。回答や解説は添付されていないことに注意してください。
新制度の対策を重視するなら最新のテキストを購入しよう
試験内容が旧制度と大きく変わらないとはいえ、新専門医制度に対応したテキストを使うことは大切です。今後傾向が変わる可能性もあるためです。したがって、最新の小児科専門医試験向けのテキストや資料を用いて対策するのがおすすめです。
また、新専門医制度における研修では定期的なフィードバックが導入され、研修手帳に記録する機会が増えました。研修手帳で記録した情報を振り返りながら、学習を進めることもひとつの手段といえます。
まとめ
新制度における小児科専門医試験は、旧制度と比較しても大きな変化はありません。これまでの傾向を踏まえると筆記試験の結果が合否に大きく影響を与える可能性が高い傾向にあります。過去問を中心に最新のテキストや資料を用いて十分な筆記試験対策をしておくことが重要です。
小児科専門医試験を受けようと考えている方は日々の研修をしっかり行い、様々な疾患、経験を積んでいき、余裕を持った試験対策を行えるように努めましょう。